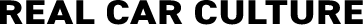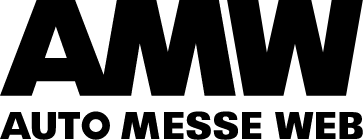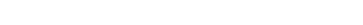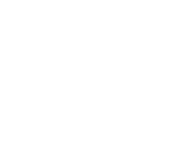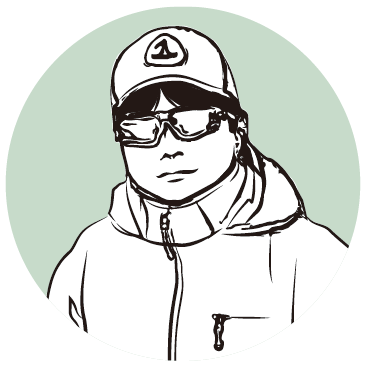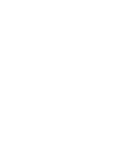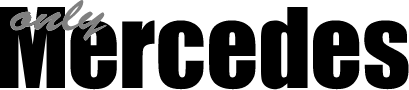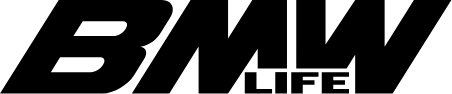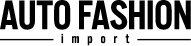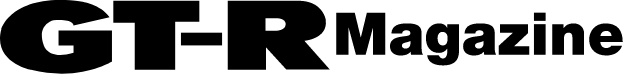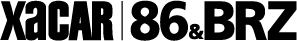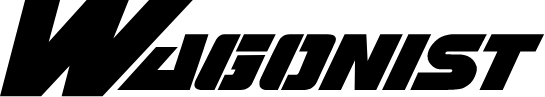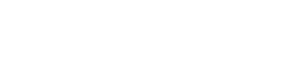正しい対処と退避場所への移動が命を守る
運転中のトラブルは突然訪れます。そんな緊急時に焦らず正しく行動できるかどうかが、命を守るカギに。安全確保のための最初の一歩から後続車への注意喚起、救援依頼の方法、そして車内に備えておきたい必須アイテムまで解説します。
安全確保の第一歩はハザードランプ点灯と路肩への停車
経験しないことに越したことはないけど、万が一に備えて知っておきたい知識。もし高速道路を走行中にクルマがトラブルを起こしたら、どのように対処してどこへ連絡するのがベストなのだろうか。
まず最初にするべきは、周囲のクルマに異変を知らせて二次災害を防ぐため、ハザードランプを点灯し、十分な幅のある路肩や路側帯に停車することだ。パーキングエリアやサービスエリアまで頑張ろうとして、何かしらの部品が外れたり火災を起こしたり、クルマのダメージを深刻にしてしまっては元も子もない。なお、安全に停車できそうなスペースがないトンネルや橋の上ならば、ハザードランプを点けたまま、可能な限り広いところまで自走しよう。
後続車への注意喚起は迅速に
クルマを停めたら、次は後続車に対して注意を促す。三角表示板と呼ばれる「警告反射板」もしくは「停止表示機材」を風圧で倒れたりしないよう注意しながら、停止車両の後方へ設置する。続いて発炎筒を点火し、本線に転がり出ないような場所に置く。そして、クルマの車内にとどまらず速やかにガードレールの外へ退避。同乗者がいる場合は、三角表示板や発炎筒の作業に付き合わせたりせず、すぐにガードレールの外へ出るよう指示するのがドライバーの務めだ。
目的は説明するまでもなく、後続車に追突されたときの被害を軽減するためで、巻き添えをできるだけ避けるためにも、クルマよりも後方で待機するといい。仮に外が猛暑だったり雨が降っていても、車内で待機するのは厳禁と覚えておこう。
通報後はガードレールの外など安全な場所での待機が最優先
自分と同乗者の安全がひとまず確保できたら、携帯電話もしくは非常電話で救援を依頼する。通報先は、事故を伴わない故障なら道路緊急ダイヤル(#9910)が一般的だ。その際は位置を把握してもらうため、上り線なのか下り線なのか、路肩にあるキロポストの数値や周辺の施設などを相手に伝えよう。
もし事故に起因する故障のときは、必ず警察(110)に。またケガ人がいれば救急(119)にも通報すること。通報を済ませてケガ人がいる場合はその救護を完了したあとは、前述のとおりガードレールの外で救援を待つだけだ。
自分で修理したり、原因を突き止めたい気持ちは理解できるけど、くれぐれも高速道路上でボンネットを開けてエンジンルームを覗き込んだり、パンクしたタイヤの交換など、何かしら作業をしようとする行為は二次災害に繋がりかねない。あとのことはプロに任せるのが最適解だと割り切ろう。
愛車に備えておきたい必須アイテムとは?
続いては、万が一のトラブルに備えて愛車に積んでおくべきものを紹介する。なお、高速道路での話につき、牽引ロープなどは割愛。
まず前述の発炎筒は、道路運送車両法で搭載が義務化されているので、有効期限が切れていれば車検を通らない(本体に記載されている)。いざというときに使えなくては意味がないので、念のためにマイカーの発炎筒の位置を確認しておこう。
もうひとつの三角表示板は、あらかじめクルマに搭載しておく義務こそないけど、高速道路で駐停車するときに使用しなければ「故障車両表示義務違反」となる。できるだけ出しやすい位置に積んでおきたい。

雨や強烈な日差しが降り注ぐときは、レインコートや帽子があれば便利だ。傘は飛ばされて事故を招く危険性があるので、風が強いときは使わないほうが無難と思われる。
また、救援まで時間がかかることも想定されるため、消費期限の長いペットボトルの水(2Lサイズがオススメ)を常備しておくと安心(高速道路上には当然のことながら飲み物の自動販売機もない)。さらにちょっとした食べ物があればよりいいだろう。どれほど入念にメンテナンスしていようとも、車両トラブルが起きる可能性はゼロじゃない。まわりのクルマや人を巻き込まない安全な対処法を、頭に入れておこう。