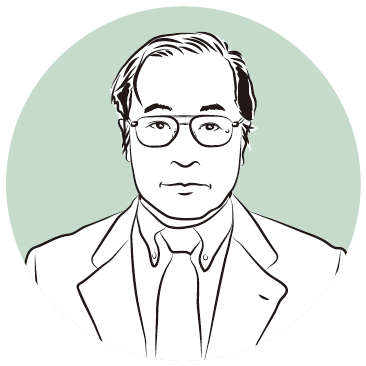70年代後半にはハイレベルなバトルへ、
FLレースの歴史とマシンの全貌を探る
前回は、70年代前半に生まれたミニF1「FLマシン」について紹介した。今回はpart.2として、70年代後半に登場してきたマシンの紹介とともに、究極へとレベルアップしたバトルについても触れておこう。
70年代前半のFLレースは、関東では茨城県・筑波サーキット、関西では三重県・鈴鹿サーキットが主戦場で、他にも静岡県・富士スピードウェイや岡山県・中山サーキット、広島県・野呂山スピードパーク(74年で廃業)、山口県・厚保サーキット(2006年閉鎖。現在はマツダの美祢自動車試験場として稼働)など、関東勢と関西勢が互いに行き来をしながら覇を競った。
72年から2年間はJAFの全日本選手権が懸けられることになったが、FL500ではなく排気量を360cc以下に制限したFJ360が対象となるなど、実情にそぐわない面もあってJAFのタイトルは2年間で終了。その後は各サーキットが独自のタイトルを掲げてシリーズ戦を組むようになり、FLの人気はさらに高まっていった。
このモノクロ写真は、筆者が学生だった頃に某モータースポーツ誌のレポーターとして取材した時の1カット。場所は西日本サーキット(現マツダ美祢自動車試験場)。
ポールポジションの畑川治選手(写真右端のNo.2 ハヤシ711)が出遅れ、2番手から猛ダッシュを見せた佐々木秀六選手(中央のNo.18 トダRS3。佐々木孝太選手の父)がトップに立ち、緒方幸雄選手(左端のNo.40 トダRS2)と中本健吾選手(その後方のNo.28 トダRS2)の戸田レーシング勢が続く展開だった。結果的には畑川選手が逆転優勝。佐々木選手と中本選手はリタイアし、緒方選手が2位というレースだった。
また、鈴鹿サーキットではフルコースを舞台に、F2レースのサポートイベントとして展開。多くの観客に見守られながらバトルするとあって人気が高まり、それに比例するようにレベルアップ。78年からは鈴鹿独自のシリーズ戦が組まれると同時に、フレッシュマンのための鈴鹿シルバーカップレース・シリーズでは、シルバーカップのFLからフルコースのFLにステップアップするのが、一つの“エリートコース”となった。フルコースのFLレースは自然に、関東勢も含めFL日本一を決する頂上決戦へと昇華していったのだ。
【ベルコ97C】
70年代序盤、FL初のモノコックフレームを持った、極めて商品性の高いベルコ96Aを投入し、関東の雄となった鈴木板金の後継モデルが97(シリーズ)。当初はスリムなノーズの97Aとして72年にデビューしたが、スポーツカーノーズにコンバートした97Bを経て、76年にはカウルワークだけでなく、サスペンションまで一新した97Cが登場。そのベルコで修業していた金子真佐一さんが独立して興したカネコレーシングの第2作目となったモデルがマキシムA-02だ。
モノコックもカウルワークも低くコンパクトに仕上げられていたのが特徴。一方、FLの草分け的存在でオートルックの最終進化形となったモデルが、サイドラジエターのアローT54Vである。カウルワークも、97Bと同様スポーツカーノーズを使用するが、そのデザインは一新。また、97Bと同じくフロントサスはインボード式だが、ロッキングアームを使っていた97Bに対してプルロッドを使ったインボードタイプへと一新された。リアはコンベンショナルなアウトボード式。
【マキシムA-02】
低くてコンパクトなボディ(カウル&シャシー)が大きな特徴のマキシムA-02。鈴鹿サーキットのS字コーナーをコンボイで駆け抜ける2台のA-02だが、ロールバーがカウルで覆われた水色の27号車が標準仕様。後方の8号車=黒いボディにGPAのロゴが映える1台は、おそらくは大柄なダニエル・ラトゥール選手(エルフの国内代理店のユニコの元社長、というよりもタレント、マリエさんのお父さんとして知られるダニエル・デマレさん)用の特別仕様でロールバーを高くしたためにエンジンカウルから突き出ているのが最大の相違点だ。
【アローT54V】
FLの草分けである堀雄登吉さんが製作した最終モデルのFLがアローT54V。前作のS31で初めて水冷エンジンを搭載、ラジエターの取付には随分苦労したようにも映ったが、このT54Vではエンジンの両サイドに、ボディと平行にマウント。前方のサイドストラクチャーはウェッジ・シェイプで仕上げるなど他とは一線を画している。
【KS-07/KS-07B】
関西におけるFLのパイオニアとなったハヤシや、当初はベルコの関西地区代理店も兼務していたベルコ・ウエスト(現・ウエストレーシングカーズ)とともに、関西勢三羽烏として活躍していた鴻池スピードの第3世代FLが76年にリリースされたKS-07(シリーズ)。78年には07Bに移行している。
愛知県江南市に本拠を構えるマナティ・レーシングサービスの処女作がFLのMK-1。70年代前半からコンストラクターとして活動してきた篠田レーシングショップの第4世代FLがSRS905。そして個性的なカウルワークでライバルと一線を画していたのがレーシングポスト・カタノのカタノFZ-09。マキF1…発表当初のF101にも似たエクステリアは超個性的だ。ハヤシ702Aを手掛けた鴻池庸禎さんが、後に独立して興したコンストラクター、鴻池スピード(KS)の、01、05/05Bに続く3代目が07シリーズ。76年にデビューした07と78年にそれを発展させた07B(黄色のマシン)の2モデルがある。両車の違いはリアのカウルワーク。コンベンショナルな07に対して07Bではリアカウルのアッパーデッキをウイングに近づけ、スロッテッド・ウイング的なトライが目新しく注目を集めていた。
鬼才と評されることの多い鴻池さんだが、シャシーに関してはコンサバ。前後のサスペンションは、ともにアウトボード式ダブルウィッシュボーンで、手堅さからいえば初期のブラバムを支えたロン・トーラナックタイプのデザイナーだった。
【マナティMK-1】
マナティの処女作、MK-1は、ベルコ時代に97シリーズを手掛けた熊野学さんが設計。コンパクトなボディに個性的なカウルをまとうが、シャシーはスペースフレームに前後アウトボード式ダブルウィッシュボーン・サスペンションを組み付けるなどコンベンショナルだ。ちなみに、Mk-1(マーク1)ではなくマナティのMと、大野和幸代表ら関係者のイニシャル、Kを繋げたネーミング。
熊野さんは現在、モータージャーナリスト&テクニカルライターとして活躍。メカニズム解説関連の書籍で健筆を奮っていることはよく知られている。
【SRS905】
70年代序盤からレーシングカーの製作を手掛けていた篠田レーシングショップ(SRS)の第4世代FLがSR 905。前作の903まではスリムなノーズでラジエターはモノコック後部の両サイドにマウントしていたが、905で初めてスポーツカーノーズ+シングルのフロントラジエターというパッケージを採用している。モノコックはスリムに仕上がりサスペンション・ピックアップのバルクヘッドが外に延長されているのも大きな特徴だ。
【カタノFZ-09】
1971年に処女作のカタノF01を製作していたレーシングポスト・カタノのファイナルウェポンが1979年に登場したFZ-09。早い段階からインボードサスペンションなど、凝ったマシンづくりを進めてきたが、FZ-09ではサイドポンツーン内部を空洞にするなど、空力的な新しいチャレンジにトライしている。
またスポーツカーノーズ+フロントラジエターと言うパッケージは、当時のトレンドだが、ルックスではライバルと一線を画していた。
当初はKEやKS、そして多数派のハヤシに新興勢力のベルコ・ウエスト(現・ウエストレーシングカーズ)らの関西勢が、ベルコやマキシムなどの関東勢に対して優勢に戦いを進めていた。が、77年にRSワタナベが投入したファルコン77Aが、その勢力図を一変させることになる。
空力的なアドバンテージを武器にストレートスピードが高かったファルコン77Aは“ファルコン・ショック”なるフレーズを誕生させたほど。当時のハヤシとKSがけん引していた関西勢を破り、78年には飯田武選手によって鈴鹿フルコースシリーズのチャンピオンに輝いている。
このファルコン77Aを打ち負かすことを目標に開発されたハヤシの最終兵器が712。空力を追求することに加えて、FLとして初めてアルミハニカム製のモノコックを採用。フレーム剛性が高くなったことでコーナリングスピードが増し、ストレートでも見違える速さを発揮した。
この脅威は“ファルコン・ショック”に対して“ハヤシ・マジック”と呼ばれ、中野常治選手(中野信治選手の父)がチャンピオンとなり、関東勢から派遣を奪回することになった。
これに対してファルコンは、80年シーズンに向けて80Aを投入、同年に小幡栄選手が再び関東勢にタイトルを奪還。翌81年には篠田康雄選手が連覇を果たしている。
この間、79年にはFJ1300がF3に移行、また80年からはFJ1600レースが導入され、コンストラクターやレーシングチームの活動も、その2つのカテゴリーに集中することになり、FLレースは衰退へと向かっていった。
【ファルコン77A】
FLレースにおける勢力図を一気に塗り替えたファルコン77A。それまでもスポーツカーノーズのFLは幾つかのモデルで登場していたが、ノーズの左右にラジエターを抱えるパッケージは、77Aが先駆けとなり、ストレートスピードの速さでライバルを圧倒した。鈴鹿サーキットのS字コーナーをコンボイで行く77Aと、後方はベルコ97C。
ノーズ前面のエアインテークの有無に注意。サイドポンツーンも前半部分の下部を絞るなど、空力的なトライが見て取れる。フロントサスはロッキングアームを使ったインボード式。アームの工作レベルも高く、高い商品性を裏付けている。
【ハヤシ712】
サイドパネルの後端を高く引き伸ばし、そこにリアウィングをマウント。独自のデザインでファルコン77Aにも負けないトップスピードを引き出したハヤシの最終兵器が712。それ以上にコーナリングスピードが高いことでライバルを一蹴。フロントサスペンションはキャスティングのロッキングアームを使用。黄色に塗られたオリジナルのダンパーも大きな武器になった。
そして最大の特徴は、FLとして初めて、アルミハニカムパネルをモノコックに使用したこと。2枚のパネルのサイドにアルミパネルのアウターを追加して、シャシー剛性はさらに引き上げられた。モノコックはサイドポンツーンも含めフラットボトムでダウンフォースは上面で稼いでいる。
【ファルコン80A】
ハヤシ712に奪われた王座を奪回したのがファルコン77Aの後継モデルとなった80A。スポーツカーノーズと呼ぶべきか意見の分かれるところで、タイヤのフェアリンクとなる両サイドとシングル・ラジエターを抱えた中央部を分けて考えた空力理論で、実際にトップスピードもさらに高まっていたようだ。フロントのサスペンションは77Aに引き続きロッキングアームを使ったインボード式だが、デザインは一新されている。
さらにリアのサスペンションも、この80Aではロッキングアームを使ったインボード式にコンバートされていた。80年には小幡栄選手がハヤシ勢を突き放して鈴鹿フルコースのチャンピオンとなり、翌81年には篠田康雄選手が連覇した。