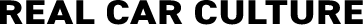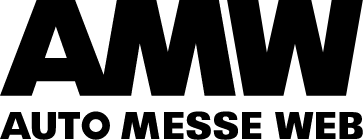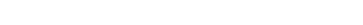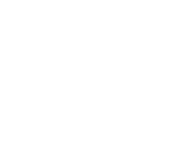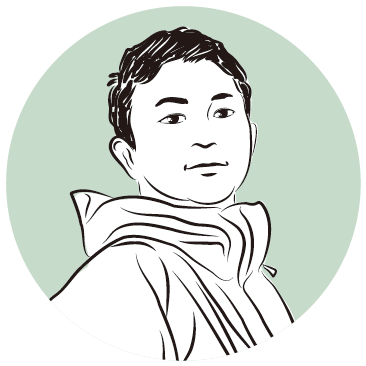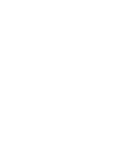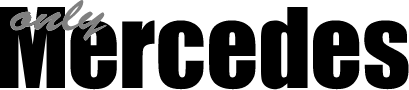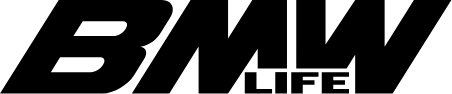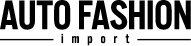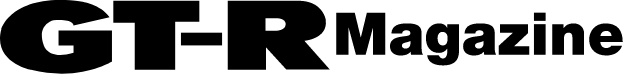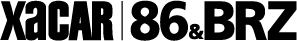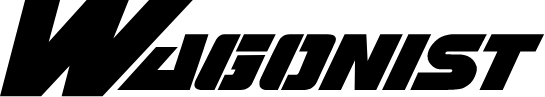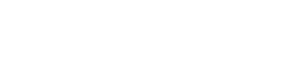逗葉道路に「ETCGO」を採用
レーシングドライバーであり自動車評論家でもある木下隆之氏が、いま気になる「key word」から徒然なるままに語る「Key’s note」。今回のキーワードは「ETCGO」。これまで料金所で支払いをしていた有料道路が突如、取り入れたシステムですが……調子が悪く混雑しているのが現状です。
わずか2kmで100円!それを現金または回数券で徴収
自宅の近所にある有料道路「逗葉道路(神奈川県)」が怪しかった。有料道路といっても、長さ2kmを通過するだけの短さ。するっと走っても1分程度で通過できる。そこが有料道路である必要性がわからないほどの短さです。
一応、道路交通法に基づく一般自動車道であり、500mのトンネルを含めて管理区間はたった2km。なのに、立派な料金所があり、立派な事務所もある。客がいるシーンも稀にしては立派な食堂も付帯している。それでも100円が徴収される。
トンネルだから迂回するには山を越えなければならず、そうすると15分のロス。じつはそのすぐそばには、もっと立派な南郷トンネルがあり、そっちは無料だ。なんだか腹が立つのである。地元では「天下りの料金徴収員のための料金所」と揶揄されている。真意のほどは不明ですが、地元ではたいそう評判が悪いのです。
しかも、ETCは使えず、料金所でいちいちコインで支払うから、もしくは古式蒼然たる回数券をちぎって渡すか……。
発展性も期待され便利になるはずが……
ところが先日、これまで頑固一徹ハイテクには見向きもしなかった料金徴収システムが、「ETCGO」なるスタイルに変更になった。いよいよ便利になるのか……と思ったものの、なんだか調子が悪い。これまでより混雑しているような気がする。
ETCGOとは、簡単に言えば、簡易型のETCのようなものです。ETCのように、停車せずに通過することはできないのですが、車載機にETCカードを差し込んでいれば、料金所でいちいち小銭を出さなくても、あるいは回数券をちぎって渡さなくても済むのです。これによって格段に便利になるはず……。
一方これは、公団側に大きなメリットがある。本格的なETCシステムに改装するには莫大な予算が必要だが、これなら設備投資を安価にできるというわけだ。しかもこれ、おおいに発展性がある。
というのは、安価に設備が整うってことは、たとえば駐車場もETCGOで料金収拾することが可能なわけだ。実際に神奈川県のウインドサーフィンW杯記念駐車場でETCGOでの料金徴収システムが始まっている。さらに発展させて、マクドナルドやスターバックスのドライブスルーの支払をETCGOで……なんてことも考えられそうです。
つまり、自動車のSuica(JR東日本エリア)、PASMO(関東の私鉄・バス、地下鉄)、ICOCA (JR西日本)。関西の私鉄(阪急、京阪、南海など)PiTaPa。 JR東海(名古屋周辺)ならTOICA。 名古屋市交通局、名鉄などはmanaca。 JR九州SUGOCA。高速道路に限定されていたETCが、SuicaやICOCAのように、交通系カードのような決済システムを目指しているのかもしれません。
結局のところ、ETCGOは利便性と引き換えに、管理される世界への小さな一歩であることはたしかです。もちろんそれは否定すべき進化ではないけれど、むしろ、どんな技術も「使い手次第」ですね。
料金を払う側が高額なETC機器を購入せねばならないのは不合理ですが、今回のETCGO化は、なんだ都合が良いように逃げ場を狭められているような気がするのは僕だけでしょうか。